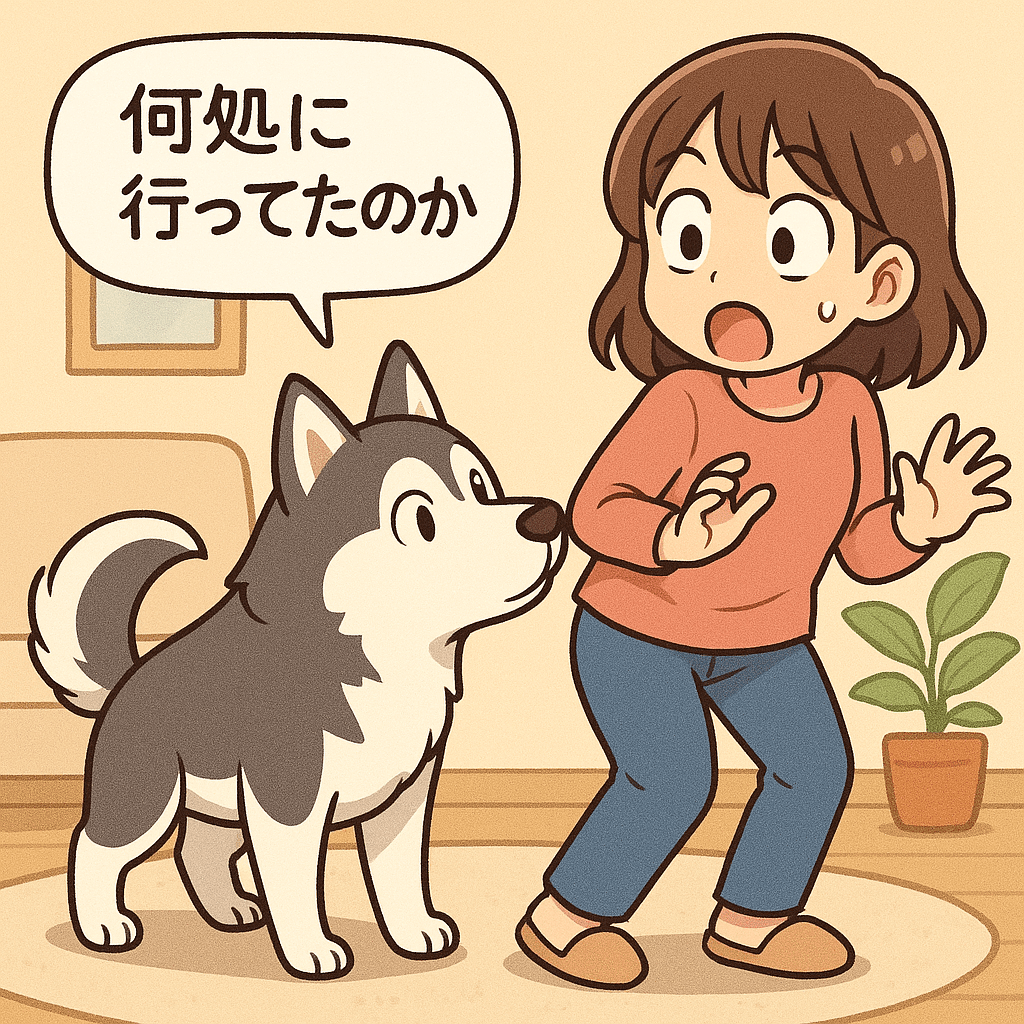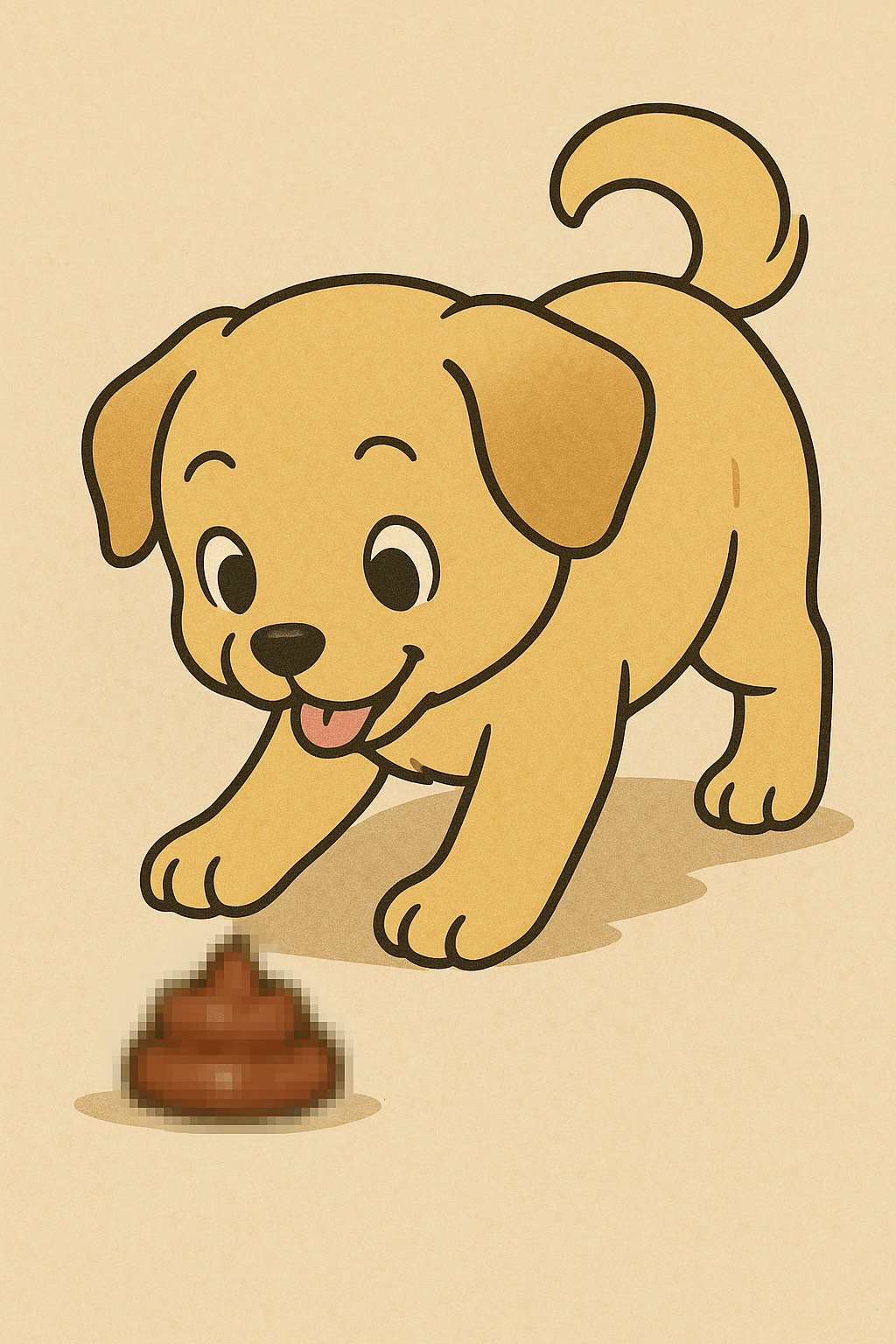この記事では、事故後の対応の流れ、飼い主様の法的責任(民事・刑事)、および行政上の義務について、初心者の方にも分かりやすくご説明します。

CONTENTS
🚨 事故直後の初期対応と行政への届出義務
愛犬が人を咬んでしまった場合、まず迅速かつ誠意をもって対応することが求められます。
1. 被害者への対応
- 直ちに救護する
- まずは、噛んでしまった愛犬を落ち着かせ、安全な場所に係留してください。
- 被害者の負傷状況を確認し、応急処置を行います。
- 被害者に対し、心から謝罪し、すぐに病院に行くよう促します。
- 治療費の支払いや誠意ある対応について約束し、連絡先(氏名、住所、電話番号)を交換します。
- 絶対にその場を離れない
- 救護をせずに現場を立ち去ることは、ひき逃げと同様に絶対にやってはいけない行為です。
2. 行政(保健所等)への届出義務
狂犬病予防法および各自治体の条例により、飼い主には以下の届出・検診義務があります。
| 義務の種類 | 内容 | 期限の目安 | 根拠法 |
| 事故発生の届出 | 事故の日時・場所、被害の状況などを所轄の保健所や動物愛護管理センターに届け出ます。 | 事故発生後24時間以内(自治体により異なる) | 狂犬病予防法、自治体条例 |
| 狂犬病の検診 | 咬んだ犬を獣医師に検診させ、狂犬病の疑いがないか確認します。 | 事故発生後48時間以内(自治体により異なる) | 狂犬病予防法 |
| 検診結果の報告 | 獣医師による検診(通常、事故直後と2週間後の2回)の結果を、保健所に提出します。 | 獣医師の指示に従い速やかに | 狂犬病予防法 |
⚖️ 飼い主が負うことになる法的責任
咬傷事故の飼い主は、主に「民事責任」と「刑事責任」という2つの法的責任を負う可能性があります。
民事責任(損害賠償責任)
被害者に対して、被った損害を金銭で賠償する責任です。
- 根拠となる法律
民法第718条(動物の占有者等の責任)「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う」 - 責任の重さ
飼い主は、「犬の占有者」として、自身の過失の有無にかかわらず、基本的に賠償責任を負います(無過失責任に近い重い責任) - 賠償の対象となる損害
治療費、病院への交通費、休業補償(仕事ができなかった期間の収入)、そして慰謝料(精神的な苦痛に対する賠償)などが含まれます。 - 責任が免除される可能性
「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」は責任を負わないと規定されていますが、犬の場合、相当の注意(リードの着用、適切な係留など)を尽くしていたことを飼い主側が立証するのは非常に困難です。
刑事責任(過失傷害罪など)
事故の状況によっては、刑法上の犯罪に問われる可能性があります。
- 過失傷害罪
適切な管理を怠った結果(過失)として人に怪我を負わせた場合、過失傷害罪(刑法第209条)に問われる可能性があります。
罰則は「30万円以下の罰金または科料」です。
飼い主の過失が特に重いと判断された場合は、重過失致傷罪に問われる可能性もあります。 - 傷害罪
飼い主が意図的に犬をけしかけて人を咬ませたような悪質なケースでは、傷害罪が成立する可能性があります。
⚠️ 再発防止と行政処分
事故後、保健所などから指導や命令が出されることがあります。
改善指導・措置命令
- 再発防止のため、愛犬の飼い方や管理方法について、行政から改善指導が入ることがあります。
- 場合によっては、特定期間の繋留(つなぐこと)の義務付けや、危険な場所での口輪の装着命令など、具体的な措置命令が出されることもあります。
- これらの命令に従わない場合も、罰則の対象となります。
咬傷犬のトレーニング
- 事故を起こした愛犬は、行動の専門家(ドッグトレーナー、獣医師など)の指導のもと、再発防止のためのトレーニングを行うことが強く推奨されます。
愛犬との生活は、その行動に全責任を負うということです。
万が一の事故を防ぐためにも、日頃から「咬まない犬」にするための適切なトレーニングと、徹底した安全管理(特に散歩中のリードの管理)を行うことが最も重要です。
もし、さらに具体的な法律や手続きについて知りたいこと、またはご心配な点があれば、弁護士や専門家にご相談いただくことをお勧めします。
🐶 飼い主様の心構え:愛犬を「牙を持った生き物」として理解する
愛犬は家族の一員ですが、本来は牙を持つ動物です。
「うちの愛犬は大丈夫」という過信が、思わぬ事故につながることがあります。
「うちの犬は絶対咬まない」という過信を捨てること
- 犬は言葉で訴えられません
- 私たち人間と違い、犬は言葉で「今はやめてほしい」「これは怖い」と伝えることができません。
その代わりに、唸る、耳を伏せる、目をそらすといったボディランゲージで不快を伝えますが、それが通じないと判断した場合、最終手段として「咬む」という行動に出ることがあります。
- 私たち人間と違い、犬は言葉で「今はやめてほしい」「これは怖い」と伝えることができません。
- 不快は突然生まれます
- 普段は人懐っこい犬でも、特定の体の部位を触られた時、寝ている時に驚かされた時、痛みを感じている時、食べ物やおもちゃを取られそうになった時など、犬にとっては不快や恐怖と感じる瞬間に咬傷してしまう可能性があります。
- 普段は人懐っこい犬でも、特定の体の部位を触られた時、寝ている時に驚かされた時、痛みを感じている時、食べ物やおもちゃを取られそうになった時など、犬にとっては不快や恐怖と感じる瞬間に咬傷してしまう可能性があります。
- 「常に犬の状態に目を配る」
- 飼い主様は、愛犬のわずかな表情や行動の変化(カーミングシグナル)を察知し、「今は不快かもしれない」と理解してあげる意識が大切です。
犬の「安全管理者」としての責任
- 犬を連れているとき、飼い主様はその犬の安全管理者です。
- 「大人しい」「人懐っこい」と過信せず、人や他の犬が近づいてきたときは、愛犬の心と体の状態を優先し、事故が起きないようにリードを短く持つ、適切な距離を取るなどの配慮を徹底しましょう。